 果たして流氷は接岸しているだろうか。
果たして流氷は接岸しているだろうか。
全国的に気温の高い日が続いている。オホーツクも同じだという。「流氷が寄る気配もない。こんな年も珍しい」と、宿の主人からの流氷情報だった。
毎年、冬のオホーツクに出かけて五年くらいになる。だが、流氷をテーマにしたベストショットは、未だに一枚もあがっていない。
流氷は、きままで、まさに風の吹くままに流され、その姿は一夜にして変わる。だから「会えるかも知れないし、会えないかもしれない」くらいの覚悟ででかけないと、落胆も大きい。
私たちが常宿にしている標津の民宿の主人は、地元の漁師でもある。揚がったばかりの魚を使った料理は、素材がいいこともあってどれも美味しい。
客の多い日は、宿の家族が普段使っているリビングに通され、そこが食堂に早変わりすることもある。
「あれは、昭和の三十四年頃だったかな。東京のある映画製作会社が流氷の映画撮影に紋別にきたことがあってね。この年には港の外には広い海水面があった。今一度流氷が岸まで押し寄せてくるかも知れないと、期待して二十日間もねばったのさ。んだども、他の仕事のかねあいもあって、とうとうあきらめて紋別を離れた。そうしたら、次の日に、しっかりと流氷がきたもんだ。うまくいかないね」
わたしたちも撮影が叶わず、空振りになることも予想される。何せ気温が高い。風が生ぬるいのである。
流氷は観光資源
流氷撮影に取り組み始めた初めの頃、師匠につれられて初めて冬の網走海岸にでかけたことがある。
その年は、気温の低い日が続いていたので、もしかしたらという、淡い期待を持ってでかけた。
到着したのは夜半だった。いつものごとく、夜を徹して走り続けるパターンで、だいぶ体も慣れてきた。
私の住む中空知から北見峠を越えて、オホーツク海岸にたどり着くには、道路がアイスバーンのところもあって、五時間くらいはかかる。道中眠らないのは、ハンドルを握る師匠だけで、参加した四人の生徒たちは、座席に座ったまま仮眠をとらせてもらう。
オホーツク沿岸では、十二月の中旬頃、漁船の大部分が陸にあげられて冬ごもりの準備をする。たいてい一月の半ば頃になると、北洋から流氷が寄ってきて、港が封鎖されるからである。
陸上から沖合をみると、天と海の分かれ目に、細く白い流氷の帯がみえる。遙か沖に見えてはいるのだけれど、その帯がいつ陸に接岸するか、地元民でも予測がむずかしいという。それが、ある朝突然に、目の前の鉛色した海が消えて、荒涼とした不気味な音のない、白い大陸に変貌するのである。
長い間、オホーツクでは流氷はやっかいなもので、漁民たちの生活をこわすもの考えられていた。
それが、流氷がもたらす海のメカニズムが解明されて久しい。流氷には、小さな植物プランクトンが一杯いて、それが春になって爆発的に増え、それを食べるエビやアミなどが大発生する。そのエビやアミを食べるために、今度はたくさんの魚が集まる。流氷が豊かな海を育んでいるという。流氷の下には魚が群れをなし、春のスケソウダラ漁は流氷の周りで行う。
「流氷早くこないかなあー」と、今では、流氷が待たれるまでになった。流氷を見学に全国から観光客があつまり、ガリンコ号が紋別港からでている。
かっては、氷漬けになった港では、歩いているひとさえ、見あたらなかったといわれている。
期待がかかる流氷なのだが、当方の都合にあわせて出現するわけではない。流氷の多い少ないは、その冬ごとに異なるばかりでなく、その日、その日の気象条件に支配されて、めまぐるしく変わる。特にオホーツク海では、動きが激しいという。
宝くじも買わねば当たらぬように、流氷も、とにかく現地にでかけなければ、会える確率もわからない。師匠の話では、大体80%の確率で、流氷があったという。
夜半の流氷撮影

海沿いの丘に車を置き、夜中のオホーツク海を見下ろす。いい具合にどす黒い海面の間に、青白い大小の氷盤や、岩のように盛り上がっている氷岩などが点在し、重なりあって浮いているのがみえる。氷と氷が積み重なっているすき間は、深いコバルト色で、いかにも流氷らしい。誠に運が良かった。
地平線につながる天空には、天気が下り坂にさしかかっていることを知らせるように、厚い雲のじゅうたんが覆い被さっていた。
撮影機材を担ぎ、よろめきながら転ばぬように斜面をおりる。降りる途中、札幌から参加した若い看護士が、足を踏み外し、前のめりに倒れ、顔面を打った。両手がふさがっていたので、とっさに手を使えなかったらしい。という怪我の状況を知ったのは、撮影を終えてからだった。それぞれ我が身を守るのに必死なのである。夜中の撮影なので、三脚は必携とあるが、実はその三脚が重たい。
いつも師匠が露払い先導役で、私たち生徒はその後ろから、そろそろと続き海岸を埋め尽くす乱氷にたどり着く。「この氷は大丈夫だから乗って」といわれても、臆病な私は足がすくむ。岸より三㍍ぐらいは離れていたか。師匠はすぐにポイントを決めたらしく早速撮影にとりかかっている。早い。やっぱりプロは違う。自然のなかでは、いっときも同じ姿を見せることはないから、一瞬をいかに切り取るかにかかる。
時折、氷同士がぶつかりあう、ギギーツという音がするだけで、波の音が聞こえない海も不気味だった。
それにしても足下が不安定きわまりない。三脚を水平に立てるにも、難儀する。つるつる氷のうえでは、転ぶと、自分の体のどこかが、こわれるか、あるいは、カメラが壊れるか、いずれかであるのは、間違いないので、よけい慎重になるのだ。

カメラ本体は、キャノンの一眼レフである。17~40ミリの広角レンズをセットした。広角は、一歩前に出て被写体に近づく事により迫力が出る。
最近、ようやくカメラをデジタルにかえた。
デジタルは、感度も自由に設定することができ、暗ければ感度をあげて、その都度、写っているかどうか、確認しながら作業ができる。
私が初めて流氷撮影に挑んだときは、まだアナログ(フイルムカメラ)だった。巻き終えて現像に出し、戻ってきてはじめて、露出が正解だったかどうかがようやくわかる。という一連のワクワク感はなくなった。だが、デジカメになって、経済的な負担が減り、なんと撮影が楽になったことやら。
防寒対策で、背中や腰や、レンズにもカイロを張り、万全の体制で望んだ初めての流氷撮影は、怪我もなく終わった。
ベストショットとはいかないまでも、フイルムで撮した夜中の流氷が、今年の自分の卓上カレンダー二月分の原画として使うことができた。

夜中の流氷は、寝る時間を削らなければ撮せない。現地にゆかねばならないことを思うと、指導してくれた師匠に頭がさがる。撮せたのではなく、撮させて頂いたことを、これからも忘れないでいたい。
地の果てに生きるもの
今でこそ警告が浸透しているが、ひと昔前なら、大人も子供も円盤氷や氷丘に乗って遊んだという。教頭が先生方の給料をポケットに入れたまま、氷に乗り、あやうく沖に流されるところだったのを、そばにいた同僚が棒をさしのべ、危機一髪で助けることができたという実話もある。
流氷の海に落ちると、そのほとんどが助からない。
戸川幸夫の「オホーツク老人」のなかの主人公、彦一老人は、流氷に乗って流されかけた愛猫と自分の命を引きかえてしまった。
冬の知床で、番屋を一人きりで守っていた孤独な老人、彦一を描いたのは、作家の戸川幸夫である。その原作を元に「地の果てに生きるもの」の森繁プロダクションの映画ができ、見て、いたく感動し書店で見つけたのが、「オホーツク老人」だった。はるか半世紀も前のころのはなしである。当時、私は限りなく孤独の縁にいた。
私は、オホーツク老人の背負った苦労とひとりぼっちの姿に、酔いしびれ、とりこになった。
そして今、私のなかでは、戸川幸夫と、敬愛する自然派作家立松和平さんに引き継がれた流氷の知床が、点から点となって太くつながっているのである。
知床が国立公園になって、今年で五〇年になり、知床峠で、記念碑の除幕式が行われたばかりである。
~地の果てに生きるものの壮絶な最期を、黒い喪服の参列者(鴉)たちが、彼らの様式に従ってこの孤独な老人の葬儀を営んでやろうと集まってきているのだった。~という下りが、あまりにも悲惨で、わたしのむねうちに刻印のように押され、消えない。
人はやはり最後はひとりなのだと、自分に言い聞かせたとき、生きる力が湧いてきた。活字の持つ力に生かされたのである。
流氷の町

何年か前の冬、羅臼港から流氷観光船(といっても、小さな漁船だった)に乗せられ、知床半島沿いに、流氷を求めて北上したことがある。行けども行けども、氷の破片さえ見つからず、ただ青黒いオホーツクの冷たい海がゆったりゆったりと、うねっているばかりであった。
カモメが頭上を旋回する。船の前で、ツチクジラが小さな潮を吹いた。
至近距離にクナシリの大きな島が見えた。予想外の近さだった。島のチャチャ岳の頂上だけは雲に隠れていた。この島がかって我が国固有の領土だった島である。「島よ帰れ」と叫びながらもう六十九年の歳月が流れてしまった。
ロシアの大統領プーチン氏が、交渉の余地があると、表明しているけれど、簡単に行かないことは、国民みんなが知っている。
春三月も終わり頃になって、知床半島を越えた流氷が、釧路の興津(おこつ)海岸まで、流れついたことがある。
官舎が海に限りなく近かったこともあり、海辺で入学前の娘と一緒に、打ち上げられたはぐれ氷に歓声をあげた。流氷のオブジェは、天然の彫刻美術館であった。
氷の形はいろいろある。厚い氷板が帆のように立っているものや、薄い氷の破片が積み上がり、まるでガラスのように透き通ってみえる。白っぽい氷は、比較的透明で、なかには青みがかっているのもあった。
この三月、師匠に連れられ十勝川河口の大津沿岸に、打ち上げ氷を撮影にいった。
大津の海は、太平洋側なので厳冬期も凍らない。だが、十勝川は十勝の厳しい寒さで、凍ってしまうのである。
野の花の群落という表現があるが、十勝川河口の打ち上げ氷も、まさに群落そのものだった。
午前3時頃現地到着、暗いなか、ヘッドキャップをつけ、打ち上げ氷が寄せ合っているところを、突き進む。雪が氷の割れ目を隠しているところもあり、足を取られて、すっぽり埋まる。そうなると、長靴がなかなか抜けない。
壮大な彫刻群を朝日が照らす。透過光は薄いオレンジだったり、透き通った水色だったり、しばしシャッターを切るのを忘れた。自然の作り出す造形美は、人知の及ぶところではない。
また、稚内の宗谷湾にも流氷が打ち上げられたことがある。たまたま東京から遊びに来ていた大学生の甥も、初めて出会った流氷に歓喜し、氷のうえで、万歳している写真が残っている。
夫の転勤先が、どういうわけか、道内の海のある町ばかりだったこともあり、むかしから流氷には縁があった。
毛ガニの上陸
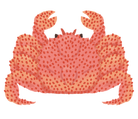
昭和四十三年四月には、広尾に転居した。狭い町営住宅に住んだ。隣人が水産加工場で働いていたこともあり、時折、捕れたばかりの魚が届き、家計の助けになった。大きなつぶ貝や、ガンジという細長いうなぎのような魚もあった。秋になると、ニシンの替わりにガンジが入った魚漬けをいただいたことがある。樽の中をのぞいたら、キャベツや白菜より、干し魚の方が多く入っており、それは美味しかった。
また、春三月、カニ漁が解禁になると、きれいな透き通るほど薄いピンク色の毛ガニも届いた。カニの足がちぎれてしまったからだという。私が夫と共にカニ好きになったのも、海のある町に住んだからか。生きの良い毛ガニの味を未だに舌が忘れていないのだ。
そのカニにまつわる、忘れられない話がある。
わたしが稚内の会社にいたころ、仕事で訪れた浜頓別の漁師から聞いた「毛ガニの上陸」のはなしである。
1974年(昭和四十九年)三月二十日頃、紋別市の北隣町、沙留にいたる国道に、毛ガニが続々と上陸して大騒ぎになったことがあるという。
二,三時間で四,五十匹も釣った人が出た。ニュースを聞いて次から次へと車が押し寄せ、毛ガニの上陸を待つうちはまだ良かった。遠浅の海に、かごを片手に入ってゆき、上陸前の毛ガニを獲る者も現れた。この毛ガニ騒動は数日で終わってしまった。
流氷が引いたあと、毛ガニが海岸にはい上がってくるのは、昭和二十五年ころまで当たり前のことであったらしい。海が豊かだった古き良き時代、にわかには信じがたい夢のようなはなしである。
私が海の町を離れて十六年がすぎた。
毛ガニは今でもその習性を忘れずに、流氷が去った海岸に人知れず上陸しているのだろうか。
流氷を探しに

標津の民宿を朝四時に出発。
夜明けの遅い二月の午前四時は、まだ未明の時間である。
尾袋沼から、細長くのびた、野付半島の先端まで流氷を探しにゆく。夏には、打瀬船が浮かぶ野付湾一帯は、雪面になっていた。
前方に、暗闇の中から動物らしい目が光る。えぞシカである。シカに会いたくても会えない時もあったのに、なんと、この増え方は異常のなにものでもない。
暗闇が徐々に青みを帯びはじめた。海の夜明けが始まろうとしていた。重たそうな雪雲が、流氷のかけらもない海に覆い被さっていた。と、にわかにすごい吹雪になってしまった。海にも陸にも私たちの車にも雪が吹きつける。雪煙が厚いカーテンとなって私たちの前に立ちふさがる。これ以上、車で進むのは危険だった。宿に戻ろう。
私は、視界のない前方に目をやり、ふと人生の旅を思い浮かべた。厳しい山坂で途方に暮れたことも数々あった。が、常に前進あるのみと自分を励まし、生きてきた。春に近い季節の吹雪は、そう長くは続かないだろう。いずれ、嘘のように止み、行く手にわずかな光が見えるに違いない。
雪が北風を連れてきたのか、風が沖から陸に向かって吹き始めるのだった。 おわり

コメント コメントは承認制です。すぐに反映されませんので、ご了承ください。