世界自然遺産・知床の「羅臼岳」で、8月14日に登山者がヒグマに襲われて命を落とすという痛ましい事故が起きました。これまで羅臼岳付近での目撃情報は多くありましたが、実際に登山者が襲われたケースは世界遺産登録後一度もなかったのです。
駆除されたヒグマのDNA鑑定が行われ、加害熊であることが特定されました。
北海道で登山をする者として、色々思うところがありましたので、山の情報サイト「ヤマレコ」に投稿しました。長くなりますが、こちらでもシェアします。
実は、私もその直後に羅臼岳を訪れるつもりでした。8月15日からの三連休を利用して、硫黄山から羅臼岳へと縦走する計画を立てていました。
胸が締めつけられるような思いで、私は連日の報道を追い続けました。15日には遺体が収容され、そして親子熊3頭が駆除されたという知らせ。テレビやネットで流れる情報や、それに寄せられる数々のコメントに触れるたび、心が痛みました。
自分が調べた事柄に似た意見ばかりが表示される「フィルターバブル」や「エコーチェンバー」など、情報バイアスを誘発する機能が働くのでしょう。
北海道のヒグマ事情
北海道には昔からヒグマが生息しています。食物連鎖の頂点にいる野生動物で、アイヌの人々は「キムンカムイ(山の神)」と畏れ敬いました。
本来ならその個体数は多くないはずなのに、近年ヒグマは増加傾向にあります。
これは山の大きさや知名度に関わらず、知床に限ったことではありません。
私が住んでいる空知管内でも連日のように目撃情報がありますが、子供を育てやすい環境になってしまったのか、畑の作物を荒らすニュースも増えています。
花も鳥も虫も、すべては子孫を残すために生まれてきました。
ヒグマもまた同じです。臆病なはずの彼らが牙を剥くのは、ただ生きるため。そして何より、子を守るため。命がけで闘う母熊の姿は、人間と何も変わりません。
しかし、知床のヒグマは人に慣れ過ぎていました。
それを知っていた人間もヒグマに慣れ過ぎていたと思います。
世界遺産に登録されて以来、知床は観光地として賑わうようになりました。華やかな空気の影で、餌付けやポイ捨てといった行為が積み重なり、野生動物と人との距離を、いつしか危ういほどに近づけてしまったと思います。
日本百名山の魅力
羅臼岳は日本百名山のひとつ。人気の高い岩尾別コースには、当日も100人を超える登山者がいたと言われていて、ほとんどが熊鈴を鳴らしていたはずです。本来なら、それだけでヒグマは姿を見せないでしょう。
それでも現れたのは、人間の食べ物の味を知ってしまった個体だったのかもしれません。最近では登山者が至近距離でヒグマを撮影した写真が出回っていました。登山者とヒグマとの距離があまりにも近いのです。今回の悲惨な事故を招く兆候はすでにあったと思います。
これまで登山者が襲われ死亡したケースは過去80年遡っても3件(1949年の旭岳1名、1970年のカムエク3名、2023年の大千軒岳1名)だったと記憶していますが、情報が容易に得られるようになった今「北海道の山=ヒグマの脅威」という強烈な印象が、今回の出来事で深く刻まれてしまったことでしょう。
犠牲になったのは、将来ある若者でした。その無念を思うと、ただ胸が詰まります。同行者の心に残った傷の深さは、誰にも計り知れません。そして、この事故は決して特定の誰かではなく、その場にいた登山者の誰が被害に遭っても、おかしくなかったのです。
もしかしたら、私だったかもしれません。
私の遭遇体験
私の無雪期の登山日数は500日ほどありますが、登山中にヒグマと遭遇したことは2回ありました。
1回目は十勝連峰の端、オプタテシケからスタート地点の白銀荘まで戻る途中でした。往復25kmほどあるロングコースですが、何度も歩いたことのある道で、ポンピ沢の激下りが始まる手前のトラバース区間でした。いくつかの沢筋があり、往路ではちょこちょこと動き回るオコジョを見かけましたが、復路で黒い物体が動くのに気付きました。
子熊2頭でした。
じゃれ合う姿はとても微笑ましいものでしたが、子熊の近くには絶対に母熊がいます。目を凝らすとハイマツの陰に大きな母熊の姿を確認しました。母熊は食事中でした。
私は少し高い所にいて、比較的距離はありましたが、下山するための道がまさにそちらの方でした。引き返して別の道を使えば完全に日没を過ぎてしまうという状況だったので、武器になりそうなストックを構え、大きな岩に隠れて笛を吹きました。
母熊は子熊を連れてゆっくりと沢筋を下りていきました。私は進行方向に向かってゆっくりと歩き始めましたが、あの時の緊張感は凄まじいものがありました。
2回目は芦別岳の旧道でした。山頂直下に広い台地があり、ここを過ぎて山頂への急な斜面を登っているとき、先ほど通ってきた台地に黒い物体がいることに気付きました。
一頭だったので雄熊だったかもしれません。あちこち移動しながら、ハイマツの実を食べていたと思います。それは優雅に、のんびりと。
食べ終わるとさっき私が歩いてきた登山道を進み、どこかへ消えていきました。
ヒグマも登山道を使った方が歩きやすいに決まっています。あと10分遅かったら、登山道で鉢合わせしていたかもしれません。登山道に落とし物が多いのにも納得がいきます。
他にもヒグマとは断定できませんが、バキバキと枝をなぎ倒す音を聞いたことは何度かあるし、強い獣臭を嗅いだこともあります。
私の場合、2回/500回なので、実際に遭遇する回数というのは決して多くないと思います。でも、絶対に遭わないということはありません。
北海道の山は手付かずの自然が残されているところが多く、それが魅力だと思います。どんなに登山者が多くても、野生動物の棲み処であることを忘れてはいけません。
自分がよそ者であることを肝に銘じて、痕跡を残さず、静かに立ち去る。それが山を歩く者の最低限の礼儀だと思います。
鈴は誰のために鳴らすのか
私は山を歩く時、鈴は鳴らさない(携帯はしている)し、撃退スプレーも持っていません。見通しの悪い所で笛を吹くことはあるし、鈴の音が聞こえたときは相手が人間であることは間違いないので、こちらの存在を知らせるために鈴を鳴らしたり、声を出します。
しかし、笹や枝が何者かによって揺らされた音だった場合、相手の大きさと距離を瞬時に感じ取らなければなりません。この時、鈴の音やラジオなどがかかっていたら、大事な音が聞き取れなくなります。おしゃべりも然り。
もちろん、スプレーを持っていた方がいいに決まっています。適切な距離でなければ効果はないにせよ、丸腰よりは心強い。けれど、結局は「遭わないこと」が何よりも大事なのです。
私はヘッドライトを使うような夜明け前や日没後には行動せず、長い休憩も山頂やテン場だけで、それ以外はほとんど歩き続けます。
同じ場所に長く留まらないこと。
それが私なりのルールです。
ヒグマも人間も、どちらかが同じ場所に留まっていれば遭遇の確率は高まると思います。
目を凝らし、耳を澄まし、匂いを嗅ぎ、足の裏で大地を感じ、他の動物が近くにいないか、五感を使うのです。ほんの数日山に身を置くだけで、感覚は研ぎ澄まされ、自然の一部になったような気がします。
山のエネルギーは時に圧倒的です。力を与えてくれることもあれば、命が削られるように感じることもあります。
自然との駆け引き、そして、調和。
それが山を歩く醍醐味でもあるのです。
生きる場所、死ぬ場所
「ヒグマに遭ったらどうするのか」
「救助する人のことを考えたことがあるのか」
「登山をしなくても生きていける」
そんな声を多く見かけました。確かに、登山は危険を伴う行為です。サーフィンやスカイダイビングだって同じでしょう。それでも、人には「好きなことをする自由」があります。家に閉じこもってゲームをするのが好きな人はそれでいいと思います。
それでも、私たちは生きている限り、誰かに迷惑をかけながら生きていくのです。
大切なのは、迷惑をかけ合ってもなお許し合える家族や仲間の存在。互いを支え合える人間関係こそ、人が生きるうえでの救いではないでしょうか。
人は誰しも、必ず死を迎えます。それならば、自分の好きな場所で、好きなことをしている最中に最期を迎えられるのなら、本望だと私は思うのです。病室のベッドで、ただ死を待つよりも。
この事故で世間は揺れ動きました。けれど、その日は「終戦記念日」でもありました。二世代前の若者たちは、赤紙一枚で戦場に駆り出され、未来のために命を捧げました。私たちはその犠牲の上に生きています。
受け継いだ命を、何に燃やすのか。
何のために生きるのか。
山を愛する人は、いくつになっても若々しい。身体を動かし、心を動かし、感動するからこそ、生きる喜びを味わえるのです。感動の大きさが、そのまま幸せの大きさになるのです。
私たちは、幸せになるために生まれてきたのです。
当事者でもないのに強いストレスがかかって身動きが取れなくなっていましたが、連休最終日の8月17日、やっと身体を動かす気力が戻りました。
心と身体は繋がっています。
どちらか一方だけを元気にすることはできません。
常に「行動が先」です。
心はそれについてきます。
悲しい事故でした。けれど、失われた命が決して無駄にならぬよう、北海道を愛し、山を愛し、自然を愛する一人の登山者として、私はこうして言葉を綴ります。
突然の別れに打ちひしがれるご家族や仲間の心が、どうか少しずつ癒されていきますように。
山を歩く私たちが、この出来事を胸に刻み、自然と向き合う姿勢をあらためることができますように。
祈りは届かないかもしれません。けれど、山に抱かれて失われた命が、永遠に大いなる自然の一部となり、安らぎに包まれますように。
合掌



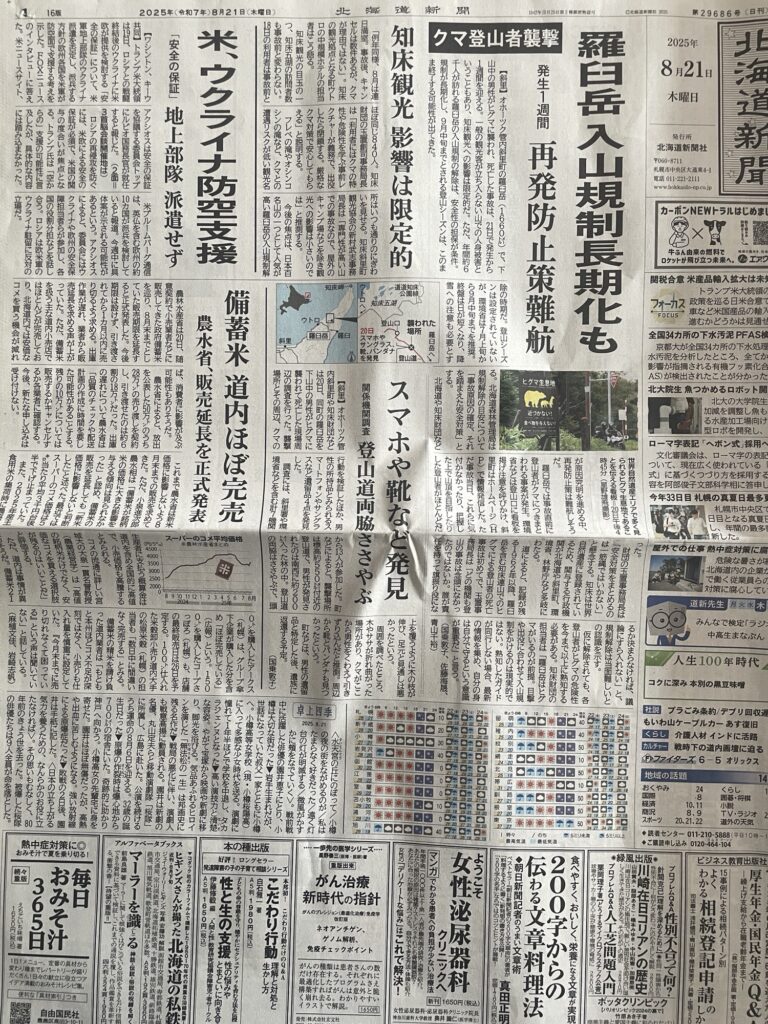

知床財団より調査速報が報告されています。


コメント